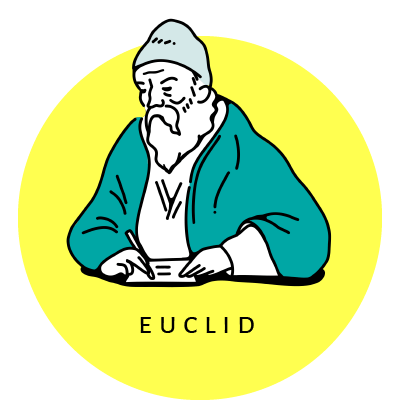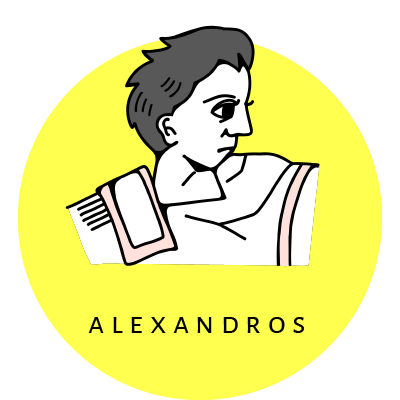プラトン とは?
古代ギリシアの哲学者
古代ギリシアを代表する哲学者プラトンは、ソクラテスの弟子にして、のちの西洋哲学に深い影響を与えた思想家です。
アテナイの郊外には、彼が設立した学園「アカデメイア」があり、その門には「幾何学を知らざる者、ここに入るべからず」と掲げられていたと伝えられています。哲学と数学の結びつきを重視したプラトンの姿勢を象徴する逸話です。
時代背景 プラトン が活躍した時代はどんな時代?
古代ギリシア哲学の最盛期
プラトンが活躍したのは、アテナイが文化的・政治的に最盛期を迎えていた古典期ギリシア。ペルシア戦争の勝利を経て、都市国家アテナイは多くの人々を引きつけ、建築、美術、演劇、そして哲学が大きく花開いた時代でした。
このような知の熱気に包まれた時代のなかで、プラトンは現実世界の背後にある「イデア」の存在を唱え、真の知を求めて思索を深めていきます。
その探究の姿勢は、現代においてもなお、多くの学問分野にインスピレーションを与え続けています。イデア論:プラトンの哲学
プラトンは、私たちが感覚で捉える現実世界を「不完全で絶えず変化するもの」と考えました。
では、本当の意味で「ある」と言えるものは何か? それが彼の唱えた「イデア」です。
イデアとは、たとえば「美そのもの」や「正義そのもの」といった、抽象的で完全な“本質”のこと。これらは感覚では捉えられませんが、理性によって認識されるべき「真の実在」だとされました。
現実の世界は、イデアの「影」にすぎず、私たちが本当に知るべきはこのイデアの世界だとプラトンは説きました。
この思想は「イデア論」として知られ、西洋哲学の礎となります。のちにある哲学者が「すべての哲学はプラトンへの脚注にすぎない」と語ったように、彼の影響は時代を超えて続いています。
プラトンとソクラテス ― 師弟の哲学
プラトンの思想を語るうえで欠かせないのが、彼の師ソクラテスの存在です。
ソクラテス自身は一切の著作を残しておらず、その教えは主にプラトンの「対話篇」によって今日に伝わっています。プラトンは、ソクラテスを登場人物として描き、その問答法を通じて倫理や正義、知識の本質といった哲学的問いに挑みました。
ソクラテスの方法は、相手に問いを投げかけ、自ら考えさせることで真理に近づくというもの。プラトンはこの方法を受け継ぎ、倫理や正義、知識の本質などの哲学的問題を探求しました。
プラトンの哲学は、ソクラテスから受け継いだ“問う姿勢”のうえに築かれているのです。
アカデメイアの開設 ー 知の共同体のはじまり
紀元前387年ごろ、プラトンはアテネ郊外にアカデメイアという教育と研究の学園を創設しました。
ここは、哲学をはじめとする幅広い学問の研究と教育の場として、多くの優れた知識人を育てた、いわば世界最古の高等教育機関のひとつです。
この学園では倫理・政治・天文学・音楽・数学などが研究され、プラトン自身も数学教育に特に力を入れていたとされます。
アカデメイアの門には、「幾何学を知らざる者、ここに入るべからず」という言葉が掲げられていた、という有名な伝説が残っています。
この学園は、後にローマ皇帝ユスティニアヌス1世によって閉鎖される西暦529年まで続き、約900年にわたって古代の学問の中心として存続しました。
プラトンの高弟アリストテレスもここで学び、後に独自の学園リュケイオンを設立し、独自の哲学体系を築いていくことになります。
「神は常に幾何学する」ープラトンの数学観
プラトンは、世界の本質は目に見える物質ではなく、「数」や「図形」の中にこそあると考えていました。
彼の思想を象徴する言葉が、「神は常に幾何学する」という名言です。
これは、宇宙の秩序や美しさが、数学的構造に貫かれているという信念を表しています。プラトンにとって、数学とは単なる道具ではなく、真理そのものに近づくための鍵でした。
彼は、数学は「役に立つ」ものではなく、「美しい」ものでなければならないとすら考えていた節があります。
著書『ティマイオス』の中で、5つの立体について述べています。これらの物体は、おのおのの面が形と大きさが等しい正多角形の立体、つまり正多面体のことで「プラトンの立体」と呼ばれています。
関連記事以下の記事で詳しく解説しています。
プラトンの対話篇 ー 哲学するための形式
プラトンの著作の最大の特徴は、「対話形式」で書かれていることです。
登場人物たちが意見を交わしながら哲学的問題を掘り下げていくこの形式は、師ソクラテスの問答法に由来しています。
プラトンは、自らの思想を直接述べるのではなく、対話の中であえて結論を明示せず、読者自身に考えさせるように工夫しました。これは彼の哲学観――真理とは他者との対話や内省を通じて近づくものである、という信念を反映したものです。
彼の著作の一つ『クリティアス』もこの対話篇の一つで、クリティアス(プラトンの曽祖父)という人物が語り手となり、古代アテナイの建国時代と、そこに関わる伝説を語ります。
この中で語られるのが、今も多くの人を魅了するアトランティス伝説です。
プラトンによれば、アトランティスは1万年以上前に高度な文明を誇っていたとされ、その記録はエジプトの神官から古代ギリシアにもたらされたものと語られています。
この物語は、古代アテナイとアトランティスの対比を通じて理想的な国家像と堕落した国家像が描かれており、後世には哲学的または政治的な寓話としても解釈されています。
関連記事以下の記事で詳しく解説しています。
プラトン の名言

教育とは、魂の目を開くことにほかならない
(原典:『国家』より)

哲学の始まりは驚きにある
知ること、考えることは、「なぜ?」と不思議に思う心から始まります。プラトンにとって哲学とは、日常の当たり前を問い直す行為でした。
(原典:『テアイテトス』)