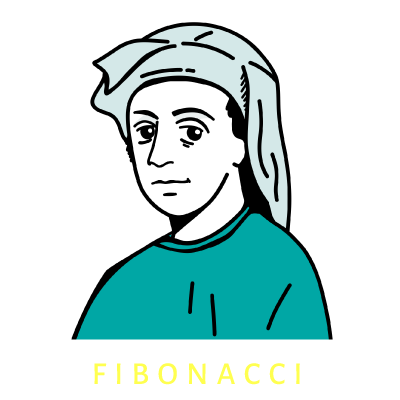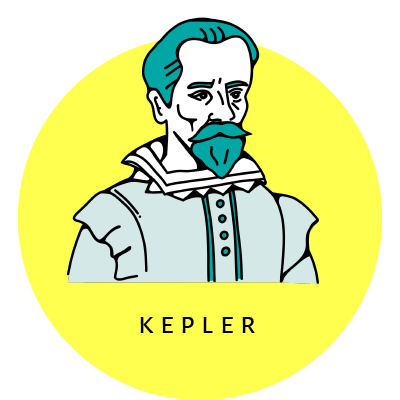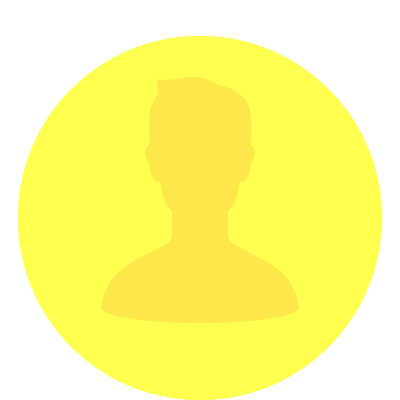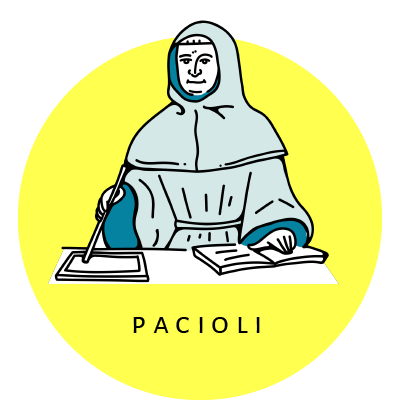フィボナッチ とは?
フィボナッチ数列の名の由来となったフィボナッチは、中世イタリアの数学者で、「ピサのレオナルド」とも呼ばれています。彼は、エジプトやシリアなどを旅し、そこで出会ったアラビア数学をヨーロッパに紹介しました。著書『算板の書』には、後に「フィボナッチ数列」として知られる数列が登場し、自然界にも見られる不思議な性質を持つことが知られています。
時代背景 フィボナッチ が活躍した時代はどんな時代?
フィボナッチが活躍した12世紀末から13世紀初頭のヨーロッパでは、都市の発展とともに商業が活発化し、東方との交易が盛んに行われていました。この時代、イスラム世界からもたらされたアラビア数学や古代ギリシアの知識が再発見され、ヨーロッパの学問に大きな影響を与えていました。特にイタリアの都市国家は、交易の中心地として栄え、知の交差点ともなっていました。
周辺背景 フィボナッチ が活躍した国とその周辺情報
フィボナッチの故郷であるピサは、当時イタリアを代表する海洋都市国家で、地中海貿易の要として繁栄していました。港町として多くのアラブ商人が行き交い、そこからもたらされた数学や計算術は、ピサに住む人々にも大きな影響を与えたと考えられます。
フィボナッチ — ピサのレオナルド
フィボナッチは、ピサで生まれた商人の息子でした。父親は北アフリカの商業都市で貿易を営んでおり、息子により良い教育を受けさせるため現地に呼び寄せます。フィボナッチはそこでアラビア語を学び、ギリシアの幾何学やバビロニアの数学にも触れました。驚くべきことに、古代エジプトの数学も伝えられており、彼の計算には「エジプト分数」と呼ばれる独特な分数表現が使われています。
算板の書(算盤の書)
ピサに戻ったフィボナッチは、学んだ知識をまとめて『算板の書』を執筆しました。32歳のときのことです。この書物の中で、彼はインド・アラビア数字(0〜9)をヨーロッパに紹介し、それまで用いられていたローマ数字に代わって、より効率的な計算体系をもたらしました。これは商人や会計士にとって画期的な変化となり、後の数学の発展にも大きく寄与しました。
また、この書には「うさぎの問題」として知られる問題が登場します。1つがいの子うさぎが毎月1つがいの子を産むとしたら、1年後にはいくつのつがいになるか? という問題で、ここで現れる数列が、後に「フィボナッチ数列」と呼ばれるようになりました。この問題の起源は、インドのサンスクリット語の詩にあるとされています。
フィボナッチ数列とは?
フィボナッチ数列とは、「前の2つの項を足すと次の項になる」という規則を持つ数列です。具体的には以下のように続いていきます。
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…
たとえば、1 + 1 = 2、1 + 2 = 3、2 + 3 = 5 といったように、どの項もその直前の2つの項の和になっています。
この数列が「フィボナッチ数列」と呼ばれるようになったのは、数学者エドゥアール・リュカによる19世紀の研究からです。彼は13世紀の数学者フィボナッチの著書に登場するこの数列に注目し、体系的な研究を行いました。
フィボナッチ数列について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください▼
フィボナッチ数列とは?~自然界にも存在する不思議な数列~
関連記事以下の記事で詳しく解説しています。