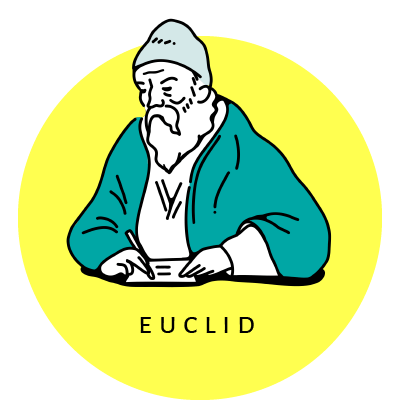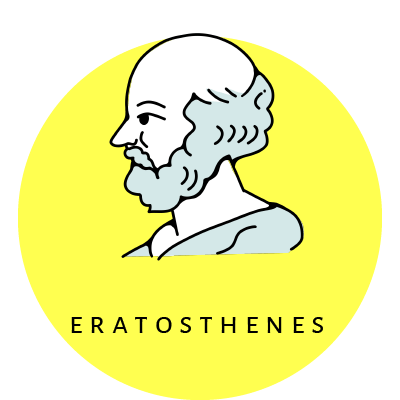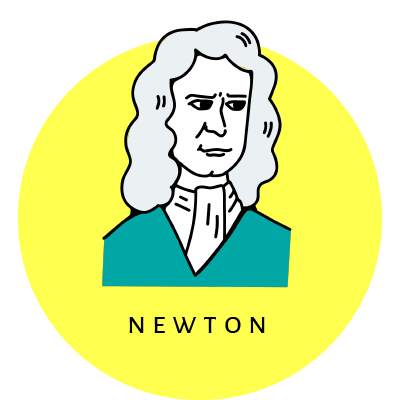アルキメデス とは?
アルキメデスが残した様々な業績
古代ギリシアを代表する数学者・科学者・発明家であるアルキメデスは、浮力に関する「アルキメデスの原理」や戦争用の兵器の設計など、科学のさまざまな分野で画期的な業績を残しました。数学の分野でも、円周率の近似値の計算、球の表面積や体積、放物線の面積の求め方など、多くの成果を残しています。
時代背景 アルキメデス が活躍した時代はどんな時代?
ヘレニズム時代
アルキメデスが活躍したのは紀元前3世紀、古代ギリシアの「ヘレニズム期」と呼ばれる時代です。
ペルシア戦争後、ギリシアの都市国家アテナイは大きな発展を遂げ、多くの人々が集まり、学問や文化が大きく花開きました。ギリシア数学もこの時期に生まれ、発展を遂げ、その後、アレクサンドリア(エジプト)へと研究の中心が移っていきます。
このヘレニズム期において、ギリシアの理論的・論証的な数学は、オリエント地域の実用数学の影響を受けて融合・変化していきました。アルキメデスはその融合を体現した人物であり、理論的な厳密さを保ちながらも、実際に武器を設計したり実験を行ったりと、応用面にも強く関心を寄せていました。
アルキメデスの原理 – 浮力の研究
アルキメデスは、液体中にある物体は、それが押しのけた液体の重さと同じだけの浮力を受けることを発見しました。これは後に「アルキメデスの原理」として知られるようになりました。
この発見には、よく知られた逸話があります。シラクサの王が金細工師に王冠を作らせたところ、金に銀を混ぜているのではないかと疑い、アルキメデスに真偽の確認を依頼しました。ある日アルキメデスがお風呂に入った際、自分の体が湯船に沈むと同時に、その体積と同じ量の湯があふれることに気づきます。この現象から、物体の体積を水の排出量で測定できると考え、王冠に銀が混じっているかどうかを確かめる方法を思いついたとされます。
ひらめいた瞬間、「わかったぞ!(Eureka!)」と叫びながら、興奮のあまり裸のまま街中を駆け出したという有名な逸話も伝えられています。
世界三大数学者のひとりとしてのアルキメデス
アルキメデスは、アイザック・ニュートンやカール・フリードリヒ・ガウスと並び、世界三大数学者の一人として広く知られています。彼の研究と発明は、古代にとどまらず中世から近代に至るまで、多くの科学者や技術者に深い影響を与えました。
彼の著作は、イスラム世界を経て中世ヨーロッパに伝わり、ルネサンス期の科学革命にも大きな貢献をしました。その功績は、数学や自然科学の発展において、今なお高く評価されています。
22/7 の秘密 — アルキメデスが求めた円周率の近似
アルキメデスの代表的な業績のひとつに、円周率 π の近似値の算出があります。
彼は、直径1の円に内接する正多角形と外接する正多角形の周長を用いて、円周の長さを挟み込む方法を考案しました。
計算には96角形などの非常に多角な図形が使われ、当時としては驚くほど精緻な手法でした。こうしてアルキメデスは、
「円周はその直径の 約 22/7 倍 である」
という近似値を導き出したのです。この 22/7 という比は、現在でも π(円周率)の近似値として広く知られています。
関連記事以下の記事で詳しく解説しています。
アルキメデスの求積法 — 積分の源流となった発想
アルキメデスの研究は、現代数学の発展に大きな影響を与えました。なかでも、図形や立体の面積・体積を求める方法、すなわち「求積」は、のちにニュートンやライプニッツによって確立される積分法の原型とされています。
彼の方法は、幾何学的な直観と厳密な論証によって支えられたものであり、「微積分の先駆者」とも称される理由のひとつです。
詳しくはWeb連載『積分の源流 アルキメデスの求積』で解説します。
関連記事以下の記事で詳しく解説しています。
アルキメデス の名言
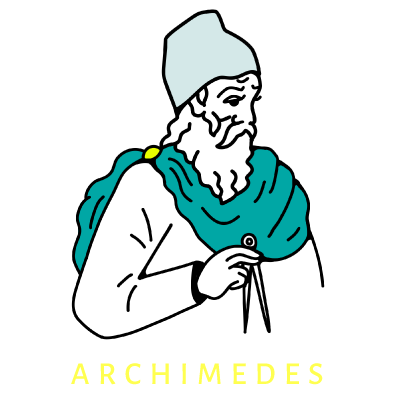
私に支点を与えよ。そうすれば地球を動かしてみせよう
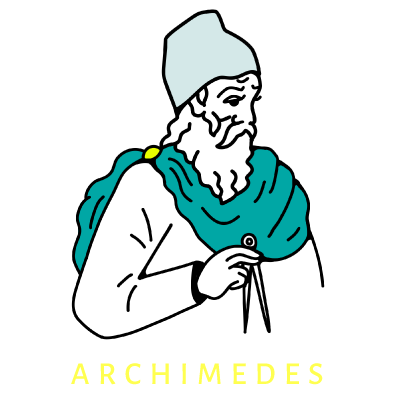
「エウレカ!(見つけたぞ!)」
王冠の密度を調べるために浴槽に入ったとき、浮力の原理をひらめいたアルキメデスが叫んだとされる言葉です。ギリシア語で「私は見つけた!」という意味で、科学史に残る最も有名な瞬間のひとつとして語り継がれています。この言葉は今日でも、何かを発見したときの歓喜の表現として使われています。