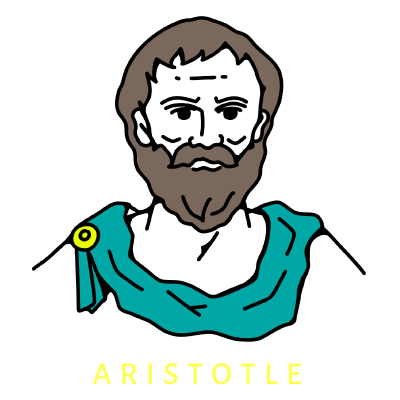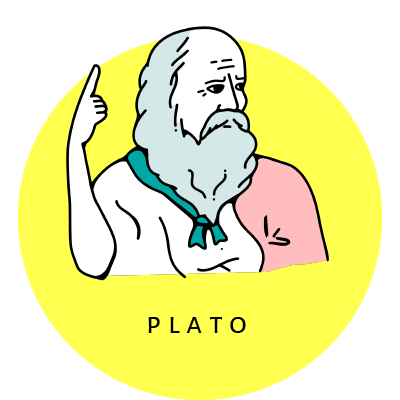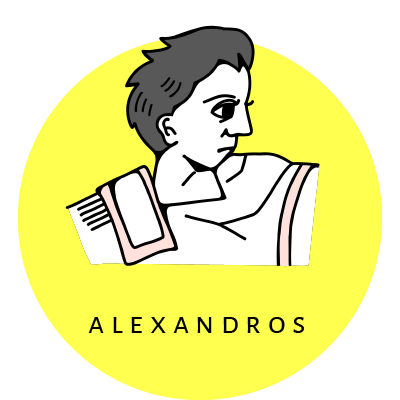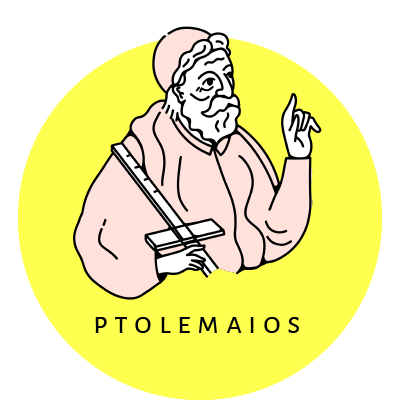アリストテレス とは?
アリストテレスは、古代ギリシャを代表する哲学者であり、自然科学・論理学・倫理・政治・生物学など、あらゆる学問分野に足跡を残した「万学の祖」と呼ばれる偉人です。
彼はプラトンの弟子であり、後にはアレクサンダー大王の家庭教師も務めたことで広く知られています。
その膨大な著作と体系的な思索は、後世の西洋思想・中世スコラ哲学・近代科学に至るまで、深く影響を与え続けました。
時代背景 アリストテレス が活躍した時代はどんな時代?
ポリスの興隆とマケドニアの台頭
アリストテレスが活動したのは、紀元前4世紀。
ギリシャ世界はペロポネソス戦争(アテネ vs スパルタ)の混乱を経て、知的・文化的な発展の絶頂期を迎えつつありました。
一方で、都市国家(ポリス)間の争いは続き、アテネの衰退に乗じてマケドニア王国が台頭していきます。
アリストテレス自身も、アテネから離れ、マケドニア王フィリッポス2世の招聘を受けて王子アレクサンダー(後の大王)を教育する役割を果たしました。
プラトンの弟子として──観念から現実へ
アリストテレスは、古代ギリシアを代表する哲学者の一人であり、プラトンの高弟としても知られています。
彼は北部ギリシアの都市に生まれ、若くしてアテネに渡り、当時の偉大な哲学者プラトンの学園アカデメイアに入門しました。約20年にわたってプラトンのもとで学びましたが、やがてイデア論に対して批判的な立場をとるようになります。
プラトンが「物事の本質はイデアという超越的な世界にある」と主張したのに対し、アリストテレスは「本質はこの現実世界の中にこそある」とし、経験や観察にもとづく探究を重視しました。
数学へのまなざし──実用ではなく美として
アリストテレスは主に哲学や自然学を中心に研究していましたが、数学にも深い関心を持っていました。彼は、「数学は実用的でなくてもよい。その美しさのために価値がある」と考え、「役に立たないからこそ高貴な学問である」と述べています。
また、彼は数学の起源についても触れており、「エジプトで数学が生まれたのは、神官に余暇があったからだ」と語っています。これは、エジプトからギリシアへの知識の伝播を認める発言でもあります。
『形而上学』に見る数と世界──ピタゴラス学派への敬意
アリストテレスは著書『形而上学』の中で、ピタゴラス学派の思想に深い理解を示しています。彼らが「数は万物の根源である」と考え、宇宙全体を音階や比率として捉えていたことに敬意を表し、次のように記しています:
「ピタゴラス派は初めて数学に関心を持ち、数がすべての物事の原理だと信じた。音楽的特性も比率として数で表現できることに気づき、宇宙全体が音階であり、数そのものであると悟った。正義、魂、知性などもまた、数の性質によって表されると考えた。」
さらに、アリストテレスは人間らしい生を送るために大切なものとして「労働ではなく、スコレー(schole=余暇・学び)」を挙げています。
このスコレーという言葉は、のちに英語の “school”(学校)の語源にもなりました。
このようにアリストテレスは、現実を重視しつつも、抽象的な真理や数の美しさに対する深い感性を持ち合わせており、哲学・自然学・数学をつなぐ存在として、古代世界の知の頂点に立つ人物といえるでしょう。
古典期のギリシア人たちが数学をどのように見ていたのか、詳しく解説しています▼
関連記事以下の記事で詳しく解説しています。
アレキサンダー大王の家庭教師
アリストテレスが哲学者としてだけでなく、歴史に名を刻む王の教育者としても知られているのは、彼が若き日のアレキサンダー大王の家庭教師を務めていたからです。
プラトンの死後、アリストテレスはアテネを離れ、各地を旅しながら知見を深めていきました。
そして紀元前343年ごろ、マケドニア王フィリッポス2世に招かれ、その王子であるアレクサンドロス(後の大王)の教育を託されることになります。
アリストテレスは王族にふさわしい教養として、哲学・倫理・政治・自然学・修辞学などを教えたとされています。
後にアレキサンダーが東方遠征を通じてヘレニズム文化の礎を築いた背景には、若き日に受けたアリストテレスの知的影響が少なからずあったと考えられています。
アレキサンダーが遠征へと旅立った後、アリストテレスは再びアテネに戻り、
リュケイオンと呼ばれる学園を開設しました。そこでは歩きながら議論する「逍遥学派(ペリパトス派)」として、哲学・自然観察・論理など多彩な分野の学問が教えられました。
王が遠征に出た後、アリストテレスはアテネに戻り、リュケイオンという学園を設立しました。