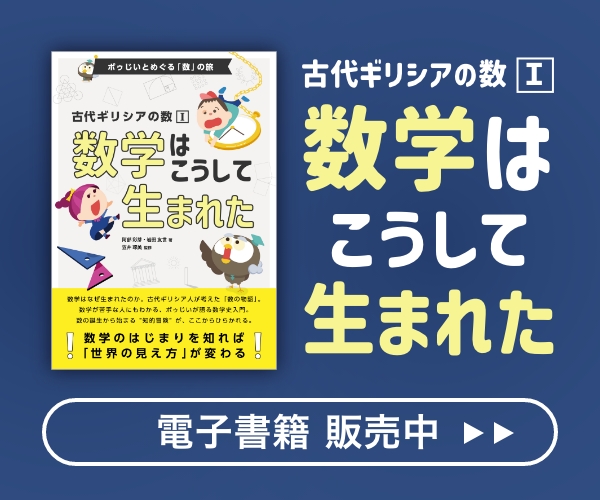1.ピタゴラスとは何者か?謎に包まれた数学者の伝記
ピタゴラスとは何者だったのか?
「すべてのものは数である」
本記事では、ピタゴラスの生涯をたどりながら、彼の思想がどのように数学の歴史に影響を与えていったのかを探ります。
彼が旅した地エジプト、そして出会った人物タレス。その道のりのなかで芽生えた、「数の宇宙」という壮大なビジョンとは?
数学の源流を辿る、知的冒険の旅へようこそ。
何千年も語り継がれる偉人の物語
今回は “ちょっとひといき・数学コラム” と題して、『三平方の定理』で知られるピタゴラスについてご紹介します。
ピタゴラスは、世界的に名の知れた古代の偉人のひとりです。かつてはヨーロッパでも、子ども向けの本などによく登場していましたが、近年は「偉人伝」自体の人気が下火になり、取り上げられることも少なくなってきました。
また最近では、「それは史実なのか? 後世の創作なのでは?」といった議論もよく見かけます。
けれども、2500年以上にわたって語り継がれてきたという事実自体が歴史といえるのではないでしょうか。そして、数学の歴史からこのような“物語”が失われていくのは、どこか寂しい気もします。
ここでは、古代ギリシアの数学者・哲学者であるピタゴラスがどのように語られてきたのか、そして彼が生きた時代や場所の背景を一緒に見ていきましょう。
ピタゴラスが生きた時代のギリシア世界
まず、ピタゴラスが生まれた当時のギリシア世界の地理と時代背景を確認しておきましょう。
ギリシア本土の東にはアテナイ(現アテネ)があり、そのさらに東、エーゲ海には大小の島々が点在しています。南へ進むと、やや大きなクレタ島があり、さらに東には現在のトルコにあたる地域、小アジア(古代ではアナトリア)があります。
このアナトリアの西岸沿いを、イオニア地方と呼びます。北は黒海、南はレヴァント地方(地中海の東岸)につながっており、さらに南下すれば、ナイル川の河口に広がる古代エジプトのデルタ地帯に至ります。
こうした東地中海沿岸地域は、古代エジプト文明とメソポタミア文明という二大文明の周辺に位置し、古くから栄えた文化圏であり、交易ネットワークの中心地でもありました。

哲学が生まれたイオニアの地
古代ギリシア世界の特徴としてよく挙げられるのが、「ポリス」の存在です。ポリスはしばしば「都市国家」と訳されますが、実際には多くが国と呼べるほどの規模ではなく、町や村ほどの大きさで、行政機構を持たない自治的な共同体に近いものでした。
それでも、ポリスの住民たちは、専制君主制ではなく、自由で平等な市民による協議制のもとで政治に参加していました。
一方で、当時のオリエント諸国では、神官階級が権威を握り、占いや神託によって物事を決定していたため、分からないことはすべて神や運命に委ねられていたのです。
こうした中、ギリシアでは「自分たち自身で考え、話し合う」という民主的で自由な風土が育まれ、自然現象や世界の成り立ちについても、論理的・合理的に理解しようとする姿勢が芽生えていきました。このような環境のもと、「自然について語る者たち」、すなわち自然学者(フュシオロゴイ)が登場します。
こうした動きが哲学の出発点とされ、イオニア地方は「哲学の発祥地」として知られるようになったのです。

ピタゴラスの生い立ち
ピタゴラスが生まれたのは、イオニア地方のエーゲ海に浮かぶサモス島です。この島は古くからギリシア人が暮らし、ピタゴラスの時代には、ギリシア世界でも有数の都市国家(ポリス)として栄えていました。
ピタゴラスは、裕福な貿易商の家に生まれ、幼い頃から各地の賢者を訪ねて学ぶ機会に恵まれていました。18歳のときに父親を亡くした後、叔父から紹介状と銀貨を託され、近隣のレスボス島に住む賢者ペレキュデスのもとを訪れます。
ペレキュデスはフェニキアに伝わる秘本を研究し、オリエントの魔術に通じた人物で、ピタゴラスに大きな影響を与えました。霊魂の不滅や輪廻転生、そして数に神秘的な意味を見出す「数神秘主義」は、ペレキュデスからの教えがもとになったと考えられています。ピタゴラスはこの出会いを通じて、生涯にわたる思想の基盤を築いていきました。
20歳のころ、ピタゴラスはミレトスを訪れ、当時すでに高齢だった哲学者タレスと出会います。
タレスは彼にこう説きました
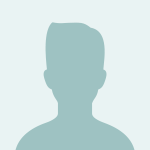
この宇宙を支配しているものは無秩序で混沌としたカオスなどではなく、合理的な説明が可能な秩序あるコスモスだ
この教えに深く感銘を受けたピタゴラスは、タレスの勧めに従い、エジプトやバビロニアなど、さらなる学びを求めて旅立つことになります。
エジプトでの学びと神秘体験
エジプトに渡ったピタゴラスは、神官たちから神聖文字ヒエログリフの読み書きを学びます。その熱意と探究心に心を動かされた神官たちは、彼にエジプトの秘儀を伝授しました。やがてピタゴラスは司祭の地位を得るほどになります。
その評判はエジプト王アマシスの耳にも届き、謁見の機会が与えられます。王の許可を得て、宗教都市ヘリオポリスや、メンフィス、テーベなどの重要な神殿を訪れることができました。神殿の奥にある「秘密の部屋」にも出入りを許され、神秘的な儀式にも参加します。
ピタゴラスはこうして、10年以上にわたってエジプトに滞在し、深遠な宗教的・哲学的思想に触れ続けたのです。
ピタゴラスとバビロニア
当時、ペルシアは小アジアからオリエント一帯へと着実に勢力を広げつつありました。ピタゴラスがエジプト滞在中にペルシア軍の侵攻を受け、捕虜としてバビロニアへ連行されたという説もあります。一方で、エジプトでの修行を終えた彼が、自らの意志でバビロニアへ向かったという伝承も伝えられています。
バビロニアは、当時のオリエント世界における文化と知識の中心地でした。ピタゴラスはこの地で、多くのオリエント諸国の楔形文字を学んだと考えられます。というのも、オリエント各地では、それぞれ独自の言語で楔形文字を用いていたからです。さらに、彼はバビロニアにおいて占星術や天文学、そして数学に関する高度な知識を吸収していきました。
こうして長い修行の旅を経たピタゴラスが、生まれ故郷であるサモス島に帰還したのは、すでに50歳を過ぎた頃のことでした。
ピタゴラスと数学への道
今回の記事では、ピタゴラスがどのような時代に生まれ、どのような人々と出会いながら数学や哲学の世界へと歩みを進めていったのかを辿りました。彼にとって数学とは、宇宙の原理や秩序を理解するための手段だったことがわかります。その姿勢は、現代の私たちが抱く「数学」のイメージとは大きく異なっていたことでしょう。
次回は、ピタゴラス学派が「数(整数)」をどのように捉え、そこからどのような思想に至ったのかを掘り下げていきます。
次回はピタゴラス学派が『数(整数)』についてどのように考えに行き着いたのかについて深掘りしていきましょう。