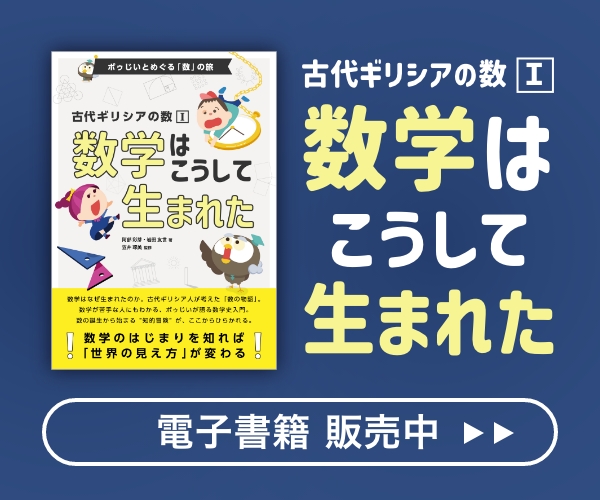4.ニュートンはなぜ微積分学を確立できたのか?科学の時代への離陸
ページ目次
知的所有権
時代によってものの考え方や習慣がずいぶん違ってきます。現代では「この事実は誰が発見した」といった“知的所有権”は重要で、特に学術的な著作においてはすでに知られている結果は誰によるものかを明確に述べる義務があります。しかしこれは現代の慣習で、古代も同じであったとは限りません。たとえば、前回のお話で述べた宇宙の天球モデルとか、「軽いものより重いものの方が早く落ちる」といった引力(重力)の問題もアリストテレスによるとされています。またその他ありとあらゆるものがアリストテレスに帰されています。アリストテレスは古代ギリシアの英知を代表する人物ですから、なんでもアリストテレスの業績にしたのであって、実際発見したのが誰であったかにはあまり関心がなかったのではないかと思われます。
先取権をめぐる争い
ニュートンは批判に対して神経過敏で、繊細で傷つきやすい性格でしたが、そのためか、たびたび激しい論争をともなうもめ事を起こしました。フックとの反射望遠鏡や「逆比例の法則」に関する確執は前に述べましたが、それ以外にもグリニッジ天文台のジョン・フラムスティードと月の観測データに関してもめ事を起こしています。最も有名なのはドイツの数学者ライプニッツとの微積分の先取権争いです。しかし、これは数学史上重要な事項なので、ニュートンの学術的な業績を解説するときに改めて述べることにします。
巨人の肩の上に立つ
このように、ニュートンの時代になると、“だれが最初に発見したか”という“先取権”は重要視されるようになっていましたが、著作の中ではこれらは触れられていません。プリンキピアは物理学においても数学においても、時代の転換点となる画期的な書物です。フックについて述べられていないのはともかく、当然言及しなければならないケプラーについても一言も述べられていません。
ニュートンの画期的な成果も、先人たちの結果の上に成り立っています。ニュートン自身も1676年に次のような有名な言葉を残しています。
「もし私が人よりも遠くを見ることができるとしたら、それはわたしが巨人の肩の上に立っているからです」
しかしこの言葉自身ニュートンのオリジナルではないのです。1621年にロバート・バートン司祭が、「巨人の方の上に立つ小人は、巨人より遠くが見える」と記していますし、1651年には詩人ジョージ・ハーバートが、1659年には清教徒のウィリアム・ヒックスが同様のことを書いています。ニュートンは揺るぎのない名声を得ていますから、このように述べても業績や名声に傷がつくことはないと思い、「代表者」として取り上げましたが、当時このようなことは普通でした。これはよいか悪いかの問題ではなくその時代の慣習の違いです。
フックによる細胞 ( cell )の発見
フックも歴史に残る偉大な科学者でした。望遠鏡や顕微鏡を改良し、顕微鏡を使った研究で生物学の基礎作りに寄与しました。フックは、コルク片を薄く切り取り、自作の顕微鏡でその薄片を観察し“細胞”を発見しそれに cell(セル、細胞)と名付けました。cell とは修道院の修道士たちが眠る独居房のことです。また、フックは30歳の頃『顕微鏡図譜』という著作を出版し大評判となります。そこには、ノミ、シラミ、ハエの目、ハチの針などの細密画が描かれていました。拡大された昆虫の図など見たことのない人たちにとって、それはまさに驚愕の世界でした。現在の私たちはノミやシラミを見たことがないと思いますが、当時のヨーロッパの人はどんな高貴な人にもノミがいたのです。しかし、ノミは飛び跳ねる点としか認識されておらず、ノミの拡大された精密画を見て、現代のSF映画で見るエイリアンのように映ったのです。多くの学者や聖職者がフックの顕微鏡を見につめかけました。この時代、生物界はまだ、神や魔術が支配する世界でした。人びとはこのような奇怪な生き物を作り出した創造主の力に感嘆したのです。『顕微鏡図譜』が出版された年は、疫病が大流行した年、ニュートンにとっての「驚愕の年」です。その後、生物学者たちは数え切れないほどの“種”を発見していきます。池の一滴の水滴のなかに数え切れない微生物がうごめいています。動物や人間の体の中にも寄生虫を発見します。「神はこのような醜悪で残忍なものまでお創りになったのか。ノアの方舟には寄生虫とかミドリムシも積んだのか。」科学が宗教から“自立”する日は間近に迫っていました。
王立協会会長としてのニュートン
ニュートンは60歳のとき、フックの死を受けて王立協会会長に選出され、亡くなるまで独裁者として権力をふるいました。歳を取るにつれまるくなるどころかますます強権的になり、少しでも不作法な振る舞いを見せると会合から追い出しました。立場を利用してさまざまな策略を講じ自分の業績の優越性を主張し、他人の業績を認めることはしませんでした。
気の毒なのはフックで、王立協会からフックの肖像画はすべて除かれてしまいました。現在フックの肖像画はほとんど残っていません。若いころフックはボイルの研究助手として、多くの結果を得ていますが、科学史ではこれらはボイル一人の成果となっています。しかし実際には実験装置を作ったり作業をしたのはフックではないかと思われています。
ニュートン が微積分学を確立できた理由
ニュートンの伝記の多くでは、ニュートンが錬金術や聖書の研究で費やした時間はまったくの浪費であり、無駄な時間であったと述べています。ニュートンの研究者が述べているように、ニュートンの死後発見された書類のほとんどは、現在から見ると、学術価値のない紙くずに等しいものだと思われます。しかしこういったことは、研究活動においては普通のことで、歴史上なされた学問上の努力のほとんどは、現在では価値がなくなっています。過去に価値があったものでも、それが改良され新しいものが生まれると、古いものは無価値となります。
本サイトでは、人類はなぜ数学をするようになったかを考えてきました。ニュートンはなぜ新しい数学(微積分学)を作ることができたのでしょうか。もちろんニュートンの才能や生まれた環境もありますが、“動機”も重要だと思います。万有引力の法則が“驚異の年”ではまだ生まれていなかったと思われるのは、そのときはまだそれを研究する動機がなかったからです。研究成果を学会で発表する、あるいは著作を書き上げるという動機がなければプリンキピアは生まれなかったのではないかと思われます。
現在の日本人の多くは無宗教で、宗教についてよく理解ができていないかもしれません。ニュートン自身は研究動機について次のように言っています。
「宇宙の法則を知ることも、錬金術も、もちろん神学も、神を研究することであり、神の御心を知ることにほかなりません。研究に対する熱意は宗教的熱意にすぎないのです。」
ニュートンが画期的な研究成果を挙げることができたのは、錬金術でも、神学でも、天文学(占星術)でも、なんでも自分が好きなことを何時間でも研究できる環境にあったからだと思われます。
科学革命の時代と古代ギリシア時代の類似点
本サイトのテーマは“数の歴史”についてであり、〔Web連載 ピラミッドの謎〕では古代エジプトの“数”について、〔Web連載 バビロニアの数〕では メソポタミアの“数”について述べています。今回ニュートンの伝記について述べたのは、この時代と古代とが非常に類似しているからです。この時代と古代とは「ギリシア古典期、ヘレニズム期」と「ルネサンス期、科学革命時代」 のことです。以下ではこれについて説明します。
科学技術の時代へ
ガリレオ・ガリレイ、ケプラー、ニュートンは科学に対する認識を一変させ、今日の科学技術時代に通じる道を切り開きました。どのように変わったのかを見てみましょう。中世までの“学問”は、人格を高めるための教養であって実用に供するためのものではありませんでした。実用上役に立つものは“技芸”といって卑しいものとされていました。大洋航海や産業の発達により、人びとは科学が産業を支えて人々の生活や国力を向上させることに気づきます。それまでは“古代の英知”を尊び「古いものが優れている」と考えていたのが、次第に「新しいものの方が優れている」という“進歩”のパラダイムを持つようになります。しかしこれは科学革命という言葉が示すほど急激に起きたわけではありません。
数学様式の変化
ニュートンたちの活躍で、数学は幾何学的思考様式から代数的思考様式へと移行していきます。『プリンキピア』は、他に例を見ないほどの絶賛を受けている名著ですが、それにもかかわらず難解で読む人が非常に少ない本でもあります。ニュートンは微積分法という新しい代数的手法を開発したのですが、この著書にはこれは用いられていないのです。記述はユークリッドの『原論』のような、古典的な幾何学的様式で書かれています。
『プリンキピア』はラテン語で書かれており、正式名は、「自然哲学の数学的諸原理」“Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” です。ここで少し単語の意味の移り代わりを見ていきましょう。米国では今でも数学の博士号は Ph.D. で、これは Philosophiae Doctor の略ですから、正確に訳すと“哲学博士”となります。ここではラテン語ではなく対応する英語で説明しましょう。現在では physics は“物理”と訳されますが、ニュートン以前のものは“自然哲学”と訳されています。自然哲学は、古代ギリシアのアリストテレスにまで遡ります。自然哲学は“自然学”とも訳されますが、自然学では観察とか実験を行いません。人間の感覚(五感)は信用できず、純粋な思考、思弁だけで判断しようという立場です。自然学と呼ぶと誤解を招く恐れがあるので、以下では自然哲学と呼ぶことにします。
アリストテレスの自然哲学
アリストテレスは古代ギリシアの古典期の終焉期の人で、エジプトやバビロニアの学問を受けつぎ、ギリシア独自の哲学をつくり上げました。エジプトやバビロニアの数学や天文学は、観察や実用から生まれたものです。学問(特に数学)の発展には、いちど実践から離れ、純粋に思考のみで理論を組み立てる必要があります。アリストテレスはギリシアの自然哲学の独自性(オリジナリティ)を強調するために、実践(計測・実験)を否定し思弁(論証・証明)を強調したのです。ニュートンは著書に“自然哲学”という名を付けましたが、この著作は自然哲学(形而上学)から“物理”を独立させた革命の書なのです。
ルネサンス期と科学革命の時代
現代人の視点で、科学革命をなしとげたニュートン、ケプラー、ボイルなどを見ると、彼らが錬金術や占星術の研究に日夜を費やしていたなどとは信じられないかもしれません。しかし実際は、教会に押さえつけられていた中世よりもルネサンス期の方が盛んだったのです。これらはオリエントから流入したものです。古代ギリシアの哲学や文芸とともに、占星術(天文学、数学)や錬金術(アラビア化学)がヨーロッパに持ち込まれました。当時ギリシアは存在していないことに注意してください。オリエント(東洋、“日の出の地”の意)に対応する語はオクシデント(西洋)で、このころは古代ギリシアもエジプトもバビロニアもすべてオリエントでした。ギリシアをエジプトやバビロニアから切り離し、自分たちの先祖と見なすようになったのは19世紀になってからです。
「科学革命によって、科学がそれまでの迷信から抜け出し優位に立った。化学と錬金術、天文学と占星術、数秘術(魔術)と数学、これらはまったく異なるものである。“術”がつくのは“前科学的”、“非科学的”であり、“学”がつくのが“学問”である」などという記述をよくみかけます。しかしニュートンの時代はまだ“術がつくもの”が全盛でした。ボイルもニュートンも錬金術に熱中しており、ケプラーもガリレオも占星術のとりこでした。
古代ギリシア時代とヘレニズム時代
同様なことが古代ギリシア時代とヘレニズム時代にもいえます。「古代ギリシア文明は、迷信などといった不可知なもののせいすることなく、すべてを普遍的な法則から導き出す合理的精神から生まれた」などとよくいわれます。このような見方は、現代人が科学革命の時代を古代ギリシア時代に投影したもので、少し美化しすぎのように思われます。ギリシアも古代社会の例にもれず、迷信深く、生贄とか秘儀や祭事をとても大切にしていましたし、戦争などの政治的判断は神託によって決定していました。
17世紀の「科学革命」は世界史において「近代の起源」を作った画期的な出来事でした。これによって西欧の列強は中国、インド、アラビアなどの他の文明圏をはるかに凌駕し、現在の科学技術万能の世界に至っているのです。しかし、18~20世紀の歴史観は、「西欧中心主義」に陥った、と西欧の歴史家自身が述べています。これはこのあと勢いを増してくる、人種主義、ロマン主義、進歩主義のことを指します。
17世紀までは、西欧は教条主義で「古代の知恵」を知識の源として学んでいました。ギリシアの哲学や文学だけでなくエジプトやアラビア(バビロニア)の占星術や錬金術を立派な学問として学び研究していました。しかし、科学革命以降、「西欧の優位」は疑いようがありません。しだいに、「古いものより新しいものの方が優れている」という進歩主義に取って代わられます。19世紀になると、エジプトや中東は衰退し、かつて文明が栄えたという面影はまったくなくなります。ヨーロッパの列強は中東に進出し利権や領土を争い始めます。これを“東方問題”といいます。この混乱のなかでギリシアという国が地上に初めて生まれます。またこのときの確執は現在のウクライナ戦争にまで尾を引いているのです。
人類はなぜ数学をするようになったのでしょうか。私たち人類がどのようにして「数」の概念にたどり着いたのか?人類の進化と進歩の歴史を辿る連載はこちら▼
PICK UP!!こちらのWeb連載もおすすめです
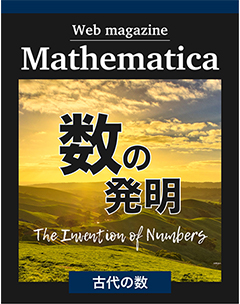
ニュートンも読んだユークリッドの『原論』とはどのようなものだったのでしょうか?
〔動画でわかるユークリッド幾何〕ではユークリッドの原論を初学者にもわかりやすい動画付きで解説します▼
PICK UP!!こちらのWeb連載もおすすめです